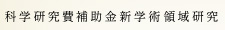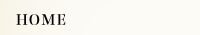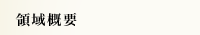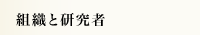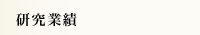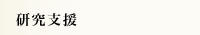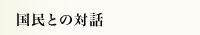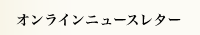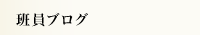HOME > オンラインニュースレター > オンラインニュースレター:2015年6月号
オンラインニュースレター:2015年6月号
2015年6月号
- e01. 「ニュースレター第6号に寄せて」 騠鍇 洋介
- e02. 「免疫四次元のメンバーに加えていただいて マラソンと研究」 椛島 健治
- e03. 「胸腺〜髄質ふしぎ発見!」 秋山 泰身
- e04. 「リガンダーとしての矜持」 穂積 勝人
- e05. 「神経系と免疫系:パラレルとクロストーク」 鈴木 一博
- e06. 「免疫細胞は脂肪細胞がお好き?」 茂呂 和世
- e07. 「免疫四次元空間ダイナミクス 参加に際して」 菊田 順一

ニュースレター第6号に寄せて (e01)
本新学術領域研究班では、班員間の情報共有と共同研究促進に資するべく、また、科学者コミュニティと一般社会への情報発信を推進すべく、オンラインニュースレターを刊行してきています。今年度の刊行予定としては、当面まず、今年度から二年間の公募研究等にて新たに参加された先生方を紹介する第6号、班会議やサマースクールなどの活動を紹介する第7号を予定しています。
この第6号では、今年度から新たに参加された先生方を対象に、自己紹介や抱負などを書いていただけないかと執筆をお願いいたしました。快く引き受けてくださいました先生方、ご多用でいらっしゃるところ誠にありがとうございました。新学術領域研究では、単なる個人研究のよせあつめではなく、活発な連携と共同に基づく新学術領域研究の科学者コミュニティへの定着と次世代研究者の育成を図ることが求められています。その観点で、このオンラインニュースレターが少しでも寄与することを願う次第です。
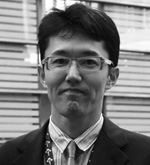
免疫四次元のメンバーに加えていただいて マラソンと研究 (e02)
この度、免疫四次元の公募班に加えていただきました椛島(かばしま)です。珍しい名前とよく言われますが、徳之島から鹿児島あたりが出身となります。徳之島に行くと椛島さんは結構いるのですが関西では稀少なため、レストランの予約などでいつも苦労しています。
さて、免疫四次元には、サマースクールで以前一度講演させていただいてからいつかメンバーに加わらせていただきたいと願ってきました。そして漸く思いが通じてとても嬉しく思っています。私が専門としている皮膚は、外界とダイレクトに接しています。そして外的刺激に対して様々な免疫応答を為しますが、その詳細を理解するためには四次元での観察に大きな価値があります。従来は、皮膚生検をしても、ある一時点における二次元の情報しか得られませんでしたから時代は大きく変わってきています。
時間軸は病態の解明に大きな役割を果たすわけですが、この時間軸というはなかなかのくせ者です。時間には、秒・分・時・日・月・年という単位があり、どれも病態を考える上で無視できない要素です。最近私たちは、物事をshort termで結論させようとしがちです。年単位の実験なんて誰もやってくれないでしょう。。。でもアトピー性皮膚炎などは年単位で病勢が動きます。
この年単位の事象を捉えるためには、研究者・観察者にどこまで忍耐力があるかが重要になってきます。最近の若い人達は(こう言い始めると私も年ですね)、自分の限界まで頑張るということをほとんど経験していないのではないかと思います。頑張りすぎて体調を壊したり、返って失敗したり、そういう経験を僕は今まで何度もしてきました。そして漸く自分の限界がわかると同時に、その限界を少しずつ広げていけたような気がします。
話は飛びますが、マラソンというスポーツに興味を持っています。最初は10kmしか走れなかったのに、今では100kmでも大丈夫になりました。京セラの稲森会長は、以前、実業団チームを持っていてそのうちの一人がオリンピックでマラソンに出場しました。そのとき途中でトップ集団から後れてしまい、結局それでも無事に入賞しました。しかしながらその選手に稲森さんは、どうして無理してでもトップの集団についていかなかったのか!と逆鱗したそうです。体力を温存して後半勝負などと言う考えは稲森さんにはまったくないようです。限界まで走り続けろ!と。これは研究にも通じる気がします。
今最大限の努力ができない人は、これからもできないよ、と稲森さんは僕らにメッセージを残してくれたように感じています。そしてその精神を僕は自身にいつも課すようにしています(いつも実行できているわけではないのですが。。。それが凡人のつらいところ)。
ということで、不束な私ですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

胸腺〜髄質ふしぎ発見! (e03)
本年度より本領域に参加させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
胸腺の髄質上皮細胞は、とても不思議な細胞だと思います。次世代シークエンスによる最近の研究では、細胞で発現可能な遺伝子の87%を発現している、とのこと。精巣も多種類の遺伝子を発現することが知られていますが、それに匹敵する種類を発現していることになります。そして、その遺伝子発現は“確率論的”であると言われています。この考えは、遺伝子発現プロファイルが1細胞ごとに異なる、との結果に基づいていると思いますが、本当に確率論で決まるのか、あるいは、これを説明できる何らかの決定論的なメカニズムが存在するのか。さらには、このような特性はどのような過程で形成されていくのか。
どこから手をつけて始めればいいのか、結構難しいところですが(図1)、先生方にご意見いただきながら、少しでも解き明かすのが目標です。

リガンダーとしての矜持 (e04)
本年度より、新学術領域研究「免疫四次元空間ダイナミクス」に参加させていただきます、東海大学の穂積です。班員のみなさまには、様々な角度から、率直なご助言をいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2年前のことですが、私は国内のNotch研究者の集まりである「Notch研究会」(2006年から毎年開催、International Meetingである「The Notch Meeting」よりも古い)でのポスターセッションにて、Notchリガンドからの視点を強調し、数人の研究仲間と議論していました。その際に、ある先生が、私が数少ないNotchリガンド(Notchそのものではなく)の研究者であることを、「Notchリガンダー」、と笑顔で評してくれました。ロボットアニメにでも出てきそうな“硬そうな”名前ですが、私は何となく気に入っていて、今でも時々、この名前を名乗らせてもらっています。
そもそも、Notchシステムの研究では、Notch受容体そのもの、あるいはそのシグナルが誘導する現象が主たる研究対象であり、そのあたりの登場分子の寄与が明らかになると、あたかもNotchシステムの寄与がすべて理解されたような“感覚”になるようです。「Notchリガンダー」としては、それは“錯覚”であり、完全な理解に向けた道半ばの状態であろうと考えます。それは、Notchリガンドの関与が明らかにされなければ、Notchシグナルが発生する「場所とタイミング」が確定しないからです。例えば、私の研究対象であるT細胞の分化におけるNotchシステムの寄与についても、Notch1遺伝子欠損によるT細胞分化の破綻を示す論文にて明示されました。しかし、この結果からは、Notch1がT細胞分化に必須であることがわかるのみで、Notchシグナルがいつ、どこで付与されるのか、という視点が決定的に欠けていました。その答えは、T細胞の分化環境を構成する胸腺上皮細胞でのNotchリガンド:Dll4の欠失を誘導し、結果、T細胞分化が完全に消失することをもって、胸腺へ未分化造血細胞が到達した際に、Dll4によってNotchシグナルが付与されることが明確になったわけです。
この視点は、免疫四次元空間ダイナミクス、を研究対象とする班員のみなさまには、きっとご理解いただけるものと思っています。すなわち、「いつ、どこで」その事象が発生するのか、との視点を、免疫応答あるいは免疫細胞分化の包括的理解に向けて持ち込んだ研究こそ、本領域の目指す一つの方向と推察しているからです。
しかしながら、この「リガンダー」としての視点は、研究を遂行するうえでの独特の難しさを供してくれます。例えば、私がよく使用する誘導型遺伝子欠損(Cre/loxP系)マウスを用いて実験を行う場合、受容体側の遺伝子欠失については、レポーター遺伝子(Creの発現により新たにマーカー遺伝子、蛍光タンパク質等、が発現)の使用により、ある程度モニタリングが可能であることから、表現型は、完全な遺伝子欠失が期待できなくとも、比較的容易に検出可能です。一方で、リガンドの場合は、環境を構成する分子であることから、少なくとも当該領域において100%の(あるいは限りなくそれに近い)遺伝子欠失が誘導されていることが求められます。当然、90%では、10%の残った分子の寄与を排除することがきわめて難しいからです。こうした制約は、「環境側」を研究対象にした際にとても顕著になり、常々、悪戦苦闘することになります。要は、実験が難しい・・・。
それでも、個体の中での本来の(!)姿を理解しようとすれば、自ずと環境側の要因に眼を向けざるをえず、こうした難点を克服したうえで、研究対象のin vivoでの正しい姿を観察したいと願っています。表に現れる現象に比較し、それを支持する環境側の研究は、多少地味に見えることが多いと思いますが、班員のみなさまが有しておられる様々な研究ツールやその使用経験を活用させていただき、環境要因としてのNotchリガンドの研究を進展させたいと考えております。班会議をはじめとした様々な機会にて、みなさまと議論できますことを楽しみにしております。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

神経系と免疫系:パラレルとクロストーク (e05)
今年度より公募班員として参加させて頂くことになりました。私は4年前に研究室を立ち上げて以来、神経系による免疫制御を中心テーマに据えています。「神経系と免疫系」というと唐突に聞こえるかもしれませんが、それには私なりの伏線があります。私は大学院時代にセマフォリンの免疫系での機能解析に携わっていました。セマフォリンはもともと神経細胞の軸索のガイダンス因子として知られていた分子です。私はこの研究経験から神経系と免疫系の間には機能分子を共有するというパラレルが存在することを知り、二つの生体システムの関係性に興味をもちました。そこで私が考えたのは、神経系と免疫系の間にはこのようなパラレルに加えて、機能的あるいは物理的な接点、つまりクロストークは存在しないのだろうかということです。「病は気から」と言われるように神経系が免疫系に何らかの影響をおよぼすことは昔から逸話的に語られてきましたし、文献的にも精神機能と免疫機能の関連性は20世紀の初頭から記述されていますので、神経系と免疫系のクロストークは存在するはずです。しかし、そのメカニズムはほとんどわかっていません。それで私は神経系と免疫系のクロストークのメカニズムを研究しようと考えたわけです。とは言え当時なんら有望な予備データが手もとにあったわけではなく、ある程度の見通しが得られるまでにはだいぶ時間がかかってしまいましたが、交感神経がリンパ節を介したリンパ球の再循環を調節する仕組みを明らかにすることができました。この研究から交感神経系と免疫系の物理的な接点がリンパ節にあることが示唆されましたが、その実態は明らかではありません。そこで本領域で行う研究では、交感神経をリンパ節を構成するストローマ細胞と捉える視点から交感神経によるリンパ球動態調節の実態に迫ります。領域の先生方とのディスカッションや共同研究を通して、この領域の発展に貢献する成果を挙げることができればと考えています。ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

免疫細胞は脂肪細胞がお好き? (e06)
2型サイトカインを狂ったように出しまくる細胞に出逢ってから10年が経とうとしている。Group 2 ILC (Innate lymphoid cell)、通称ILC2と呼ばれるようになったこの細胞は見つけようとして見つかったものではない。当時博士課程3年生で研究テーマが決まっていなかった私は「自分は何を研究したいのか」を模索する毎日だった。「何をやってもいいよ」という寛容なボスの言葉を鵜呑みにし、今考えるとゾッとするが、別段焦ることもなく気の向くままネズミと戯れる毎日を過ごしていた。その頃免疫学のことは全く分からなかったが、免疫細胞についてふしぎに思うことが2つあった。1つは「なぜリンパ節は脂肪に包まれているのか」、もう1つは「腹腔内に投与した細胞はどうしてちゃんと全身に行くのか」である。1つめについては、リンパ球をリンパ節から分離するときに感じたことで、どんなリンパ節でも脂肪組織につつまれていて、これをきれいに剥がしてあげないとぐっと細胞数が減ってしまう。また、胸腺も骨髄も加齢と共に脂肪細胞が浸潤することが切片を作製するとよくわかる。このことから、脂肪と免疫細胞にはまだ誰も知らない秘密があるのではないかと思うようになった。2つめの疑問は、細胞を移植する時に感じたことで、私は当時尾静脈内投与派だったのだが、ラボには腹腔内投与派が多数いた。免疫細胞は血液からいれるからこそ全身を駆け巡って戻るべき場所に戻るのだと主張する私に、腹腔内投与してもちゃんと戻るべき場所に戻るからいいでしょう、という腹腔内投与派。なんとなく尾静脈のほうがいい気がするもののこれに反論する術を持たずとても悔しい気持ちがしたのを覚えている。ここから生まれたのが、血管が開口しているわけでもない腹腔からどうやって細胞は全身に移動するのか?という疑問である。1の疑問と2の疑問を併せて気ままに腹腔内の脂肪組織、腸間膜をいじるようになり、期せずして見つかったのがILC2である。
ILC2自体はすっかり私の手を離れ、続々と新しい報告が飛び交う今日この頃である。しかし、最初の疑問、免疫細胞と脂肪細胞の謎は一向に答えがみつからない。だから私は今回頂いたこの領域班での研究する機会を使わせて頂き、脂肪組織に存在する謎のリンパ組織FALC(Fat-associated lymphoid cluster)の謎に挑みたい。ねちっこく、マニアックに、油にまみれて2年間を過ごさせて頂く所存です。

免疫四次元空間ダイナミクス 参加に際して (e07)
この度、新学術領域研究「免疫四次元空間ダイナミクス」に公募研究として参加させていただくことになりました、大阪大学の菊田と申します。私は、研修医・リウマチ内科医として3年間病院で働いた後、大学院に進学し、生体二光子励起顕微鏡を用いて生きた骨組織内部を観察する方法論を立ち上げた石井優先生のもとで研究を開始しました。関節リウマチや骨粗鬆症における骨破壊に興味をもっていた私は、破骨細胞による骨吸収の現場をin vivoで可視化するべく技術開発を行い、生体二光子励起イメージング系を改良することで、骨破壊が起きている骨の表面部分を詳細に可視化する系を開発しました。その結果、骨表面上での破骨細胞による骨破壊過程をリアルタイムで観察することに成功し、破骨細胞による骨吸収制御機構をin vivoで明らかにしました。大学院卒業後も引き続き、骨の蛍光生体イメージング技術を用いた研究を行い、生体内における免疫細胞の時空間的な挙動の可視化と動態解明に取り組んでいます。
本領域では、班会議やサマースクールなどを通して、多方面で御活躍されている先生方とたくさんディスカッションをさせていただき、幅広く学ばせていただければと思います。今後とも御指導御鞭撻の程どうぞ宜しくお願い致します。